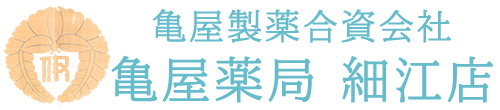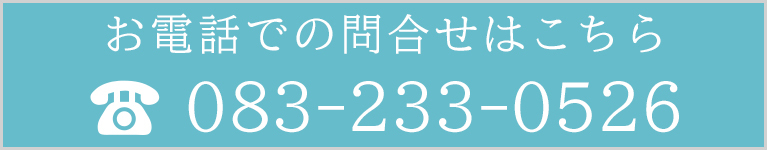会社案内
代表挨拶

伊藤家の歴史は、鎌倉時代、嘉禎年中(1235~37年)に、藤原鎌足の流れをくむ伊藤左衛門尉盛成が、長門国目代として京都から当地に下向したことにより始まります。戦国時代から江戸時代初期にかけて朝鮮や中国から漢方薬をはじめ様々な品物を買い求めて商いを手がけていました。次第に外国からの買付けが難しくなると薬屋に専念するようになりました。この時慶長9年(1604年)が亀屋製薬合資会社の始まりだと言われています。その後、長府藩の医師片山致新と亀屋喜三郎事伊藤餐霞堂(第15代当主伊藤喜三郎)が、慶長15年(1610年)に鉛丹、胡麻油、萄薬等を混ぜて作った致新膏(硬膏剤)を蛤の貝殻に入れて販売し、あかぎれ、吸い出し等の特効薬として評判となり、寒さが厳しい北国で珍重され、北前船で全国に運ばれたと聞いています。致新膏という商品名は、医師片山致新の名前からつけられたと言われています。戦後は医学の著しい発展、医薬品の開発の進歩、病態の変化、生活環境の改善等により需要が減少すると共に、厚生省の医薬品製造基準改訂等諸般の情勢により昭和52年(1977年)に製造を中止しました。
薬業界は、薬剤師の永年の願望であった医薬分業を推進する時代に入り、乗り遅れないように苦労し、商業環境の変化と共に、ドラックストアの進出が著しくなり、薬業界も一変し、薬局は「くすり」を売るだけの時代から分業の推進により、医療の一端を担う薬剤師として世間から認められるようになってきました。今日まで薬局を継続してこられたのは、お客様第一の精神で対応してきたことではないかと思います。
また、社団法人下関市薬剤師会会長、社団法人山口県薬剤師会副会長、社団法人日本薬剤師会代議員等の役職を勤め、薬業界の発展の一翼を担うことができたことは幸せに思います。
今後、薬業界は厳しい時代が続くと想像されます。市民のニーズにこたえられる薬局になること、「鶴は千年、亀は万年」と言われている言葉のように市民から愛され、これからも歴史が続いていくことを願っています。
亀屋製薬合資会社 伊藤家第24代当主
伊藤 長一(享年84歳)
会社概要
| 会社名 | 亀屋製薬合資会社亀屋薬局細江店 |
|---|---|
| 代表者名 | 伊藤 文一 |
| 設立 | 1940年9月13日 |
| 創業 | 1604年2月 |
| 所在地 | 〒750-0016 山口県下関市細江町2丁目1-9 |
| 電話番号 | 083-233-0526 |
| FAX番号 | 083‐233‐0527 |
| 事業内容 | 医薬品販売・調剤など |
| 従業員数 | 5名 |
| 店舗数 | 1店舗 |